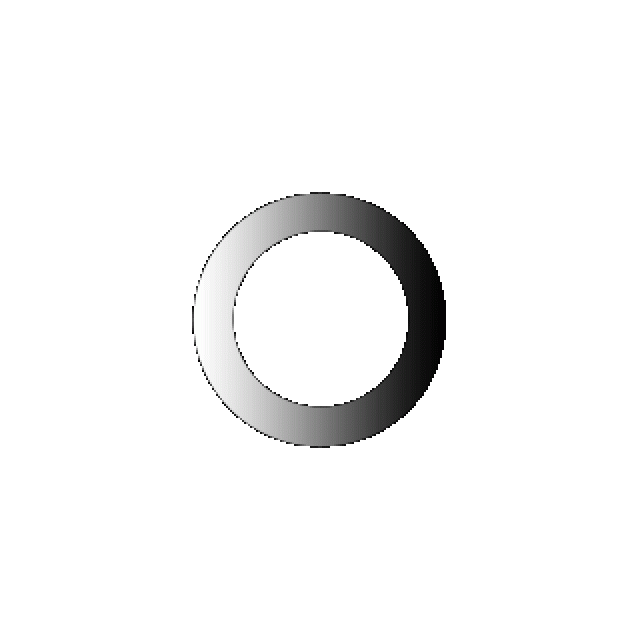「あなたの特命取材班」の舞台裏(前編)
2020年6月30日Slow News Report

今すぐ聴く
あなたの特命取材班
速水:Slow News Report今日お話を伺うのは西日本新聞の記者 坂本信博さんです。西日本新聞は福岡県にある新聞社ということで、今日は電話でお話を伺っています。今日は「記者に調べて欲しい素朴な疑問」をリスナーに呼びかけていますが、それはこういうスタイルの取り組みを西日本新聞が続けているということなんです。今日はそのお話をうかがいますが、その名も「あなたの特命取材班(あな特)」。これはどういうものなのでしょうか。
坂本:あな特は西日本新聞が2018年1月からスタートした企画なんですけれども、LINE を使って記者が読者と繋がっての双方向のやりとりと、新聞社の取材力で読者の疑問や社会の課題の解決を目指す課題解決型の調査報道で、我々はジャーナリズムオンデマンドJODと呼んでいます。
速水:あな特を始めた当初から、大きいスクープをそこから探すんだということだったのか、それとももうちょっと身近な話題みたいな感じのアプローチだったのでしょうか。
坂本:両方の思いあったんですけれども、今までの新聞というのは、読者はこれは知るべきだというニュースと、記者が読者に知らせたいというニュースに重きを置いていきました。この二つはとても大事ではあるんですけれども、一方で読者が知りたいということとそれは重なってるのかなという疑問がありました。それで読者が知りたいことをまず募集して、そこから読者起点の調査報道を始めようということでスタートしたのがあな特です。
あな特がきっかけでかんぽ生命不正販売の問題が明らかに
速水:あな特をきっかけに社会に大きなインパクトを与えるスクープも生まれているという話なんですが、例えばかんぽ生命の不正販売問題がありました。これは高齢者相手に保険商品を詐欺に等しいような、しかも組織的に売りつけるという問題が去年大きな問題になりました。このかんぽ生命の不正販売問題ですが、このきっかけが読者の声だったそうですね。
坂本:そうなんです。まさに今日6月30日に日本郵政グループがかんぽ生命不正販売で2448人が処分したという発表があったと思うんですけれども、元々は2018年4月にあな特がスタートして夏に入った頃、一本のメールが来ました。それはかもめーるという暑中見舞いはがきについての郵便局員からの調査依頼で、自腹営業を強いられて困っている。夏のボーナスを使って暑中お見舞いはがきを買うなど、ノルマを達成するために大変な苦労があるんだという話がありました。それを西日本新聞の社会部の記者が自分が取材したいと手を上げてやり取りをする中で、確かにかなりきついノルマを課せられていて、しかも日本全国の郵便局員の方、家族の方も大変な思いをしているということがわかりました。そこで暑中見舞いはがきの自腹営業ということを記事に書きました。そうする中で郵政グループは自腹営業をやめますということにつながったんですね。それでまた取材をしていく中で、暑中見舞いはがきとか年賀状も大変なノルマがあるんだけれども、実はもっとノルマが重いものがあると。それはかんぽ生命で、ノルマを達成するために高齢者を騙すような形で不正に販売を続けてきたという実態を複数の郵便局員の方が明らかにしてくれました。そこで記者がその方に会いに行ったり、お話を伺っていく中で、二重払いの不正な契約をしているという内部文書を入手することができました。その後報道していって今のかんぽ生命の問題が社会に明らかになっていったという実態があります。
速水:これは記者として、まさに目の前で話がどんどん大きくなっていくのを目の当たりにしたわけですよね。
坂本:同僚がずっと丹念に取材をしていく中で一つ一つ明らかになっていったんですけれども、あな特で記事が出たので、郵政側が警戒をして箝口令を敷いたんですね。報道に内部の事を漏らすなという文章を出しました。ただその文章そのものを LINE とかメールで送っていただいて、それもまた記事にして、という形で、ついに郵政側も事実と認めざるを得なくなってトップが辞任したり、今日の処分につながったりしたわけです。やはり世のため人のためになりたいと思って記者になっていたんですけども、読者の方たちと一緒につくっていく報道だなというの今回特に感じました。
速水:今の話を聞くと、最初に自腹営業であるというところを取り上げたところから広がっていくわけですよね。まずそこを取り上げなかったら、もしくは自腹営業の記事でやめていたら、そして日本郵政がクレームをメディア側に出したところでやめていたらと、いろんな if があって、それを全部突破してきたからこそこれだけの問題になった。そういうところが今の話だけでも非常に恐ろしいというか、その報道スタイルじゃなければ、ひょっとしたらなかったかもしれないですよね。
身近な問題も記事に
坂本:我々はあな特通信員と呼んでいるんですが、あなたの特命取材班のLINE のフォロワーの方が16000人以上おられます。そういった方々から11000件くらいの調査依頼が寄せられているんですけれども、本当に双方向のやり取りができるので次々に情報が寄せられてきます。あな特には一つ基準がありまして、困っている人がいるかどうか、そしてその人の困りごとが他の人にも共通するのかどうかということ、それそのものがニュースなんだというスタンスです。だから何か不正が明らかになったかどうかというのもニュースなんですけれども、こういったことで困っている人がいるんだということがニュースなんだということで取材を続けてきました。
速水:ということはかんぽ生命の不正販売のようなインパクトの大きいものだけでなく、もっと小さい記事をいっぱいあるわけですね。
坂本:そうですね。たとえばホタル族といいまして、家庭内が禁煙でマンションのベランダに出てタバコを吸う方がいらっしゃいます。その方の煙が隣の家に流れてきて困ってますという、今までだと新聞の記事に取り上げなかったような話なんですけれども、困っている人がいるということがニュースなんだということで報じていくなかで、じゃあどうしたらその問題を解決していけるんだろうということでいろんな読者からご意見があって、また続報を出していくということもありました。
速水:なるほど。ちなみにホタル族は解決に至ったんですか。
坂本:これがなかなか解決が難しいのかもしれませんけれども、何気なく吸ってきたタバコで誰か困っている人がいるかもしれないと気付いてくれたら、それが解決の糸口になるのかなと。ですので、新聞社で何かを解決するというよりは、困りごとを社会に伝えて、そこからいろんなアクションがあって解決につながっていけばいいなと考えています。
速水:なるほど。解決そのものよりも、こういう問題で困っている人がいるという議論を接続していくというのがメディアの一つの役割という中で、新しいやり方かなと思います。いま、あな特の見出しをいくつか見せていただいているんですが、僕が気になったのが「キラキラネームを改名したい人いませんか」という見出し、これはどういう内容の記事なんでしょうか。
坂本:これはユニークな名前の方が15歳になったら家庭裁判所に行って手続きをすれば改名できると。それで実際に改名した方を LINE で募集して、その方に取材をしていてどういう経緯で改名したのか、キラキラネームでどんなことが困ったのかとか、そういったことを報じてきました。名前ってそれぞれの価値判断にもよるものなので、何かはっきりした答えがあるわけではないんですけれども、おもしろおかしくこんな変わった名前の人がいるみたいな冗談のネタにしがちなんですけども、その方々のやはり人生がかかっているといいますか、いろんな思いがあるということを改めて掘り起こして伝えた記事でした。
地方紙というメディアに対する危機感からうまれたあな特
速水:あなたの特命取材班が企画として立ち上がった経緯はどういうものだったのでしょうか。
坂本:そもそも私自身が西日本新聞の記者、地方紙の記者になって20年くらい経った頃にかつてない危機感を感じたのがひとつのきっかけでした。それは一つは読者の新聞離れです。紙の部数がどんどん減っていって読者がどんどん減っていく。そしてもう一つは記者の地方紙離れです。優秀な後輩たちが地方紙に限界を感じてテレビ局とか中央紙に移っていくということがしばらく続いた時期があったんですね。そういうことによって新聞の迫力が失われていくという危機感がありました。企業とか行政に取材にいく中で、新聞社が取材に来たということが以前は一定のインパクトを持ってたんですけれども、その迫力がこのままだと失われてしまうんじゃないかという危機感があって、新聞の原点に帰って一人を大切にするというと、読者もそして記者も大切にする企画をしようということで始めたのがあな特でした。
速水:迫力が失われたというのは、例えば新聞の取材ですといって訪ねていっても答えてくれないということがあったりするんですか。
坂本:一時期あったんですね。あな特を始めて2年半になるんですけれども、先日若い記者が取材に行ったところ、名乗る前に「あな特ですか?」と役所の人から警戒しつつ言われたそうです。我々新聞社が強いわけではなくて、新聞社と一緒に有権者や市民の方がいるということが、企業や役所の方にも伝わって、これは無視できないということで対応してくれているという現実があります。先程のかんぽ生命の不正販売の問題も、一つ郵政側がアクションを起こせば、それがLINE やメールであな特に情報が寄せられてくるということで、郵政側もこれを無視できないと思ったんじゃないでしょうか。
速水:ひょっとしたら管轄省庁のトップとかから圧力をかければマスメディアを抑えられるみたいなことがありえる世の中かもしれない。でもそれが読者だったらそこを抑えられないということかなと思います。西日本新聞ではあな特専属チームが取材しているんでしょうか。
坂本:いいえ違います。あえて専属チームを置いてません。編集局の記者が基本的に原則として誰でも参加できる手上げ方式をとっています。記者たちはどうしても日々向き合わなきゃいけない仕事がある中で、自分の価値観でこれは是非取材したいと思えるものを、記者がベテランも若手も手を上げていられるようにしたいということでやっています。読者から届く LINE は全ての編集局の取材を担当する記者に同時に共有されるようになっていまして、その中で、いわば早い者勝ちで返信をした人がそのネタを取っていくという形です。なので、ある記者はこれはニュースではないと思ってスルーしても、別の記者がいやこれはニュースだと思って手をあげれば、その記者にとってはこれはやらされ仕事ではなくなるので、熱量を持って仕事ができるということがあります。
速水:例えばこういうものは取材しちゃだめだよみたいなルールとかってあるんですか。
坂本:基本的にはないです。西日本新聞は九州の新聞なので、基本的に守備範囲は九州ではあるんですけれども、実は先日ペルーから取材依頼がありました。その方は日系ペルー人の首都圏に住んでいる大学生の方なんですけれども、大学の研究のためにペルーに行っている中で今回のコロナ禍で飛行機が取れなくなってしまって帰ってこれないと。その方は日系ペルー人だったので、日本政府のチャーター便にも乗れない、助けてくださいということで、あな特に調査依頼があって、やりたいと言った記者が外務省に取材したりする中で、日本に居住基盤がある方についてはチャーター機に乗れますよというように改めて、彼は日本に帰って来れるようになったということもありました。
速水:日々の通報のなかで、これはガセだろうということもあるわけですよね。
坂本:最初そういうのがたくさんあるんじゃないかなと思ったんですけれども、思ったよりもないです。私が記者になった頃は、社会部110番という企画がありまして、社会部に専用の電話番号があって、そこに困りごととかを寄せてくれというものがあったんですけれども、30本電話を受けて、実際記事になるのは一本あるかどうかでした。しかも一本ので電話につき30分話を聞くということがあったんですけれども、LINE という事が正解だったらと思っているのが、 LINE というのはFacebook とか Twitter とちょっと性格が違っていて、電話に近い感じですね。友達とか家族とやり取りをする延長線上で新聞記者とやり取りしているということなんです。新聞記者をわざわざ騙すために自分のアカウントを使おうという方はあまりいなくて、やっぱり赤裸々で切実な相談を寄せてくれていることがすごく多いです。世の中にこんなに困っている人がたくさんいるんだなということと、新聞はオールドメディアという人もいますけれども、まだまだ我々は頼りにされているんだなということを実感できています。
速水:興味本位で「月曜から夜ふかし」とか「探偵ナイトスクープ」に送ってくれよ、みたいなものが来たりすることはないんですか。
坂本:そういうものもあります。以前、九州で犬を飼ってはいけないという伝説の島があると。その島では本当に犬を飼っていないのかというのがあって、実際に記者が二人で島に渡って、一軒一軒ピンポン押して回ったという、柔らかネタもやってます。「困っていることと」いうのも一つ基準があるんですけども、もう一つは読者が知りたいことにストレートに答えると。そして答えがその時分からなくても、ここまで調べたけどわかりませんでしたということも含めて書いています。
地元に寄り添う取材力こそが新しいメディアのあり方を切り開く
速水:最後に地方新聞社との連携みたいなことも西日本新聞はやられているという話をお伺いできますでしょうか。
坂本:このあな特のジャーナリズムオンデマンド、JODの手法を全国のローカルメディアにシェアをしていまして、JODパートナーシップという緩やかでしなやかな連携を組んでいます。全国で23社27媒体、北海道から沖縄まで仲間が各紙にいます。そして同じような取り組みをしていて、面白い記事をお互い交換しあったり、自分のエリアを超えた調査依頼についてはシェアしたりとか、これは全国で一斉に取り組めそうだという内部告発や情報があれば、それもまたみんなでシェアをして取り組んでいます。
速水:新聞に限らず、ラジオなんかも本当にリスナーにが困っていることに寄り添っていくというのは、非常にこれからのメディアの方向性を予感させてくれるやり方なんだろうなと思って今日はお話を伺いました。
坂本:私自身は、以前は地方紙の記者というのはなんとなく中央紙や通信社よりも下なのかなという印象があったんですけれども、実はそうではなくて、そういう地域に寄り添える取材力を持っているローカルメディアこそがこれからの報道を切り開けるんじゃないかなと今は思っています。
速水:明日もこの続きを伺うことになるんですが、明日はリスナーから募集している質問に対して、こんなことは調査するんですか?みたいなことを具体的に伺っていきたいと思います。
坂本:内容によっては取材班にシェアして、実際に取材させていただくこともあるかと思っています。
速水:リスナーの方々のモチベーションもかなり上がると思います。坂本さんどうもありがとうございました。
関連タグ