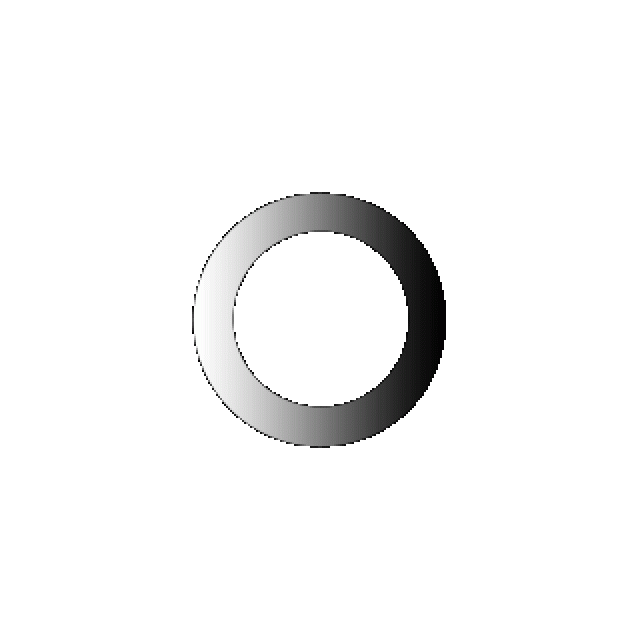コロナ禍のアメリカで、ジャーナリストができること
2020年10月27日Slow News Report

速水:今日のテーマは「コロナ禍のアメリカで、ジャーナリストができること」です。アメリカのカリフォルニアで活動を続けているドキュメンタリー映画作家 ジャーナリストでもあります、フロントラインプレスの大矢英代さんにお話を伺います。大矢さんはドキュメンタリー映画作家として『沖縄スパイ戦史』などの作品がある監督でありながら、ジャーナリストでもあるんですよね。
大矢:元々は沖縄の民放で報道記者をしていたんですけれども、5年間米軍がらみの事件事故などを取材をしていました。実はその前にも学生時代から沖縄戦の取材をしていたんですけれども、そこでもうひとつの沖縄戦といわれる「戦争マラリア」という、日本最南端の八重山諸島での戦争の歴史を取材をしました。波照間島に住み込んでルポを書いたりしながら取材を続けてきました。
速水:そして今はカリフォルニア大学で客員研究員をされながら取材をされているということで、ちょっと前までカリフォルニアにもいらっしゃったんですよね。
大矢:そうなんです。まさにコロナ禍をアメリカで経験しまして、山火事の最中にも3週間家から出られない生活をしていました。
速水:山火事の報道は日本でもすごいされていましたけれども、本当に家の周り近くでおきていたんですか。
大矢:そうです。太陽が出ない生活が3週間ぐらい続いて、灰が降ってきて家の中にいてもマスクをして換気をしながら生活をするという日々でしたね。
速水:街中に出られなかったという話ですが、それ以外でも例えばマスクをつけている状況みたいなものも東京とカリフォルニアでは違いますよね。
大矢:やはりカリフォルニアも大きな州なので、町によってもコロナに対する姿勢は違うんですけれども、コミュニティという意識が非常に強い地域では、みんなでコロナを封じ込めていくんだという姿勢があります。一方で保守の人達が住む街に行くと、やはりマスクはしない。個人主義というのが顕著に出ている町もありまして、特に私がこの半年住んでいたフレズノという街は、ロサンゼルスとサンフランシスコの間にあるちょうどカリフォルニアのおへその部分になる町なんですけれども、なかなかマスクしている人に出会わなくて、やっぱり自分の身は自分で守らなきゃいけないという生活でしたね。
速水:東京に来てかなり驚くことも多かったんじゃないですか。
大矢:びっくりですよね。マスクをしている人がほとんどじゃないですか。それに消毒液がそこら中にあったりとか、体温計で測って37.0℃を超えていたら入れませんとか、徹底ぶりがやっぱりすごいなと思いました。
速水:今日も放送局の入り口でおそらくピピッとデジタル機器による体温とマスクのチェックを受けてきたと思うんですが、今日はそういうデジタル機器による監視カメラの話なんかもお伺いしたいんですが、まず家から出られないステイホームではジャーナリストって何もできないですよね。
ステイホームのなかでジャーナリストが取材をするには
大矢:1月から3月までは一時的に日本にいたんですけれども、3月にアメリカに戻った時にはまだアメリカの状況は今よりはマシだったんですよ。ちょうどパンデミックが始まったあたりで、街を歩いていれば「アジア人がいる」というような目で見られ始めたぐらいの時期だったんですよね。そういった中で、だんだんとコロナが広がっていって、最初にサンフランシスコ周辺のエリアがロックダウンになってしまいました。それで私は南部に下がってきて、フレズノという地域にいたんです。そこならば不自由な生活はなく取材ができるかなと思っていたんですが、やがてカリフォルニア全部がロックダウンになってしまったので結局家の中で過ごす生活になってしまいました。
速水:そんな中で取材をして記事を書いていくという手法を模索してきたと思うんですが、東洋経済オンラインに今月「日本人がゾッとするアメリカ超監視社会の現実」という記事を書かれていますよね。これはいわゆる足で稼いだネタではないことをテーマに書かれた記事ですよね。
大矢:そうですね。やはりステイホームの間にジャーナリストとして何ができるかなと思い続けた結果、オンラインでできる取材ということを模索し始めたんですね。そういった中で今年の9月の下旬に調査報道国際会議というのがオンラインで開かれました。これは国際 NGO で IRE (Investigative Reporters & Editors=調査報道記者・編集者協会)という、アメリカのジャーナリストを中心にして、調査報道を専門にしている世界各地の記者たちが加盟する組織なんですが、そこで最新の取材手法を共有しあったり、取材についてそれぞれが出した記事などを語り合ったりするような場所なんです。そこが毎年会議をやっていたんですが、今年はコロナの影響で全日程一週間まるまるオンラインで開催しますということだったんです。これに私は参加をしまして、世界から3000人が参加したんですけれども、なんと日本人は5人だけでした。その数にも驚いたんですが、一方でコロナ禍でみんなジャーナリストが共通して家から出られないという困難な状況に置かれている中で、それでも自宅からできる調査報道の可能性は広がっているとみんな言うんですよ。つまりオンラインでできる調査報道というのは、様々なウェブサイトやデータベースなどがあって、それをどうやって上手く使うかがポイントなんだということなんですよね。その辺りのテクニックを学ぶ中で、「警察の監視」という問題が浮かび上がってきたということですね。
速水:例えばブラックライブズマターのニュース映像なんかを見ると警察官がみんな首からカメラを下げている。あれは基本的には警察官自身の行動が全部記録されているということで、ブラックボックスになりがちな室内での捜査の状況なんかも録画していたりすると思うんですが、そういうこととはまた違う、警察による監視みたいなものがあるそうですね。
いまアメリカで起きている警察による監視
大矢:そのボディカメラというのは、オバマ政権下で非常に普及したものなんですよね。つまり警察が絡む事件や事故について、後々の検証のためということで付けたボディカメラだったはずが、テクノロジーの発達とともに相手を分析するためのデータを収集するというような役目に段々と変わってきたということなんです。
速水:パトカーなんかにもついていて、周囲の状況が常に監視カメラの中に収められている。それをのちに分析する時に、監視対象であるとか、その時は監視していなかったとしてもあとから遡ってチェックすることがで、捜査に活用できるということなんですね。
大矢:つまりそういうことですよね。エレクトリック・フロンティア・ファウンデーションというNGOがあるんですけれども、ここの調査員の方が調査報道会議の中で講義をしまして、そこに参加して話を聞いてきたんですけれども、人の顔を自動で読み込んで分析をする顔認識機能ですとか、カメラの機能がこの10年間で飛躍的に伸びたと。また、先程お話のあった、ボディカメラを導入している州が全米で1348箇所あるとか、全米各地で警察の体に装着されているビデオカメラで自動的に通行人や職務質問している相手の顔を読み込んでいるということなんですね。市民としては警察に監視されてる一方でいいのかという思いが出てきますよね。そういった中で、今年の7月に、ある画期的なデータベースが立ち上がりました。オンラインで誰でも見られるんですけれども、「監視の地図」というタイトルのウェブサイトで、英語では「アトラス・オブ・サーベイランス」というサイトなんです。開くと全米の地図が出てきて、そこに12種類の監視ツールが書かれています。これはボディカメラとか、警察の制服に着用するボタン型監視カメラとか、ナンバープレートを読み込むシステムだとか、盗聴アプリだとか、そういったものをどの州のどの警察署が使っているかが一目でわかるデータベースなんです。これを作ったのがエレクトリック・フロンティア・ファウンデーションという NGO なんですけれども、市民を監視する警察を市民が監視するという動きが今年出てきているということですね。
速水:警察がいつからそのツールを導入し、どういうことをしているのかということを把握することの重要性みたいなことはあると思うんですが、他にも家にいながら何かしらの取材をするツールにもなっているそうですね。
大矢:そうですね。コロナの前でしたら直接警察に行ってデータを求めたりとかいうことができたんですけれども、コロナになった今はそのオンラインにあるデータを使って調査報道を進めていくということですね。今までジャーナリストが独自にやっていたことを、他の NGO だとか団体が既に調査をしてくれて、データを提供してくれているということですよね。それを元にして独自に取材を進めていくということです。やっぱり調査報道というと、いわゆる国家権力の内部に潜り込んで秘密を取り出してくるというようなイメージがあると思いますけれども、実際は公になっている情報で知られていない情報の中にたくさんの重要なものがあるんですよ。この「監視の地図」を作った団体も、国際会議の中で話をしてくれたんですけれども、使われているデータはすでに警察が公開している情報、あるいはフェイスブックとかツイッターなどで「こんなシステムを導入しました」というものを拾い集めて一つのウェブサイトにまとめたということなんですよね。
大学生が警察の監視を監視するサイトを立ち上げた
速水:「監視の地図」誰が作っているものなんでしょうか。
大矢:驚いたんですけれども、実は大学生たちが作っていたそうなんですよ。ネバダ大学リノ校という大学で将来のジャーナリストを目指す大学生たち200人、それに加えて大学教授や現役のジャーナリスト達が協力をして、計500人がこのデータベース作りに参加しているんですね。どういうやり方をしたのかというと、このウェブサイトの計画をしたエレクトリック・フロンティア・ファウンデーションがネバダ大学の教授たちに協力を呼びかけて、ウェブサイトを作ったそうなんですよ。そのウェブサイトに学生が登録をすると、毎回20分から30分くらいの、オンラインの検索で見つけられるような質問が出てくるんです。例えば「カリフォルニア州ではいつボディカメラを導入しましたか?」とかですね。そういうような質問に学生たちが答えると単位をもらえたり、ボーナスポイントをもらえたりする。そういう中で5500件のデータを収集して作ったということなんですね。それからこの学生たちはデータジャーナリズムの専攻だそうなんですよ。この10年間でデータジャーナリズムというような問題意識が非常に高まっていて、沢山の数字の羅列でしかないデータからどんな意味を読み解いていくか、というようなことを学生時代からやっているんですよね。ですから、学生たちにとってもこのデータベース作りは、自分たちの将来のキャリアにもつながっていきますし、学びにもなるんです。
速水:権力と監視といった場合、一方的に権力の側だけが監視していることでどんどん非対称性を生んでいくみたいなことがあるんですが、アメリカの状況の話をする中で、警察が監視するのって正しいじゃないかと、ひょっとしたら日本ではそういう印象ってあったりすると思うんです。ブラックライブズマターで非常に問題になったのは人種差別の問題として、黒人が警察に殺されているんだよという話で、日本では黒人の問題としてとらえている部分があるんですが、そもそも警察のあり方が日本とアメリカでは違う所ってありますよね
大矢:そうですね。私自身もアメリカに渡って一番驚いたことなんですけれども、警察による事件や事故が非常に多いんですよ。例えばアメリカの NGO で、警察による暴力の統計を収集して公開している Web サイトがあるんです。Mapping Police Violenceというウェブサイトですけれども、そのデータによりますと、今年の10月までの10ヶ月間にアメリカ全土で874人の市民が警察によって殺されているんですよね。これは肌の色に関係なく市民がこうやって警察に殺されている。それが犯罪の可能性があったとか、容疑があったかということは置いておいて、そもそもそういう暴力を振るっていいのかという問題がやはり根底にあるんですよね。
速水:なるほど。公開されているデータをまとめて見やすい形で公開する。それをジャーナリストが、それこそステイホーム中でも遠隔地で起こっていることを統計データなどから知ることができるわけですね。おそらく日本とアメリカ、どちらも同じ事が起こっていると思うんですが、マスメディア不信、ジャーナリズム不信なんかがある一方で、新しいデータジャーナリズムへの信頼、期待みたいなものがアメリカではあるんですかね。
ジャーナリズムに対する市民の意識
大矢:そうですね。まあアメリカのジャーナリズムが 100点満点かと言ったら全くそんなことはなくて、もちろんたくさんの問題をはらんではいるんですが、基本的にジャーナリズムの土壌というものが日本とアメリカで大きく違うなと思うんですよね。それはいくつか大きな要素があると思っていて、一つは今日お伝えしたような「監視の地図」を作るような市民たちがいること。つまり市民が、自分たちが主権者なんだと。権力者に支配される社会ではなくて、自分たちが権力者を見張って、正しく政治や警察権力が運用されているか見張っていくんだという意識が社会の大前提としてあるということですよね。二つ目は、そういうようなウェブサイトとか NGO にきちんと募金をしていく文化があるということ。良質なジャーナリズムにはお金がかかるんだということで、市民たちが1ドル、2ドル、10ドルと、ポケットマネーからお金を出して、自分達が良質な報道を支えていくという意識があるんですよね。ワシントンポストやニューヨーク・タイムズとか、アメリカで調査報道を一生懸命頑張っている主要メディアがありますけれども、そういうものの土壌にこういう市民の力があるんだということが日本のジャーナリズムと大きく違うなと思いました。
速水:そういう調査報道への理解であるとか、市民の後支えみたいなものが近年進んでいるんですね。
大矢:元々ジャーナリズムを支えるんだという意識がアメリカにあるんですよね。それは民主主義には正しいジャーナリズムが必要なんだという意識があるんですよ。ただ近年のテクノロジーの発達とともに市民もテクノロジーを駆使して権力者を監視し始めたと。
速水:冒頭で調査報道国際会議というものが今年行われて、日本からは5人しか参加されなかったという話がありましたが、報道というものが今変わろうとしている中で、大矢さんがこれからやろうとしていることを最後にお伺いしていいですか。
大矢:今回の会議でも英語ネイティブじゃない方々がたくさん参加されていたんですよ。もちろん上手な英語とは言えないまでも、きちんと自分の言葉で発信して学ぼうという姿勢が皆さんあったんですよね。そういった中で、やはり日本のジャーナリストももっともっと日本の外に出て、日本の外でどんなジャーナリズムが今主体となってきているのか、他の国の報道で自分たちが学び取れるものってなんだろうかとか、外から学んでほしいと思うんです。地球規模で起きているメディア不信を、自分たちがファクトを持って直して支えていくという、そういう意識を持っていかないといけないなと思うんですよね。そういった中で私はアメリカから日本の視聴者読者に向けて世界の動きを伝えていけるようなジャーナリストでありたいなと思っています。
速水:最後にお伺いしますが、今取材しているテーマは何ですか。
大矢:5日後にはアメリカに戻るんですけれども、大統領選挙か待っているんですよね。私の中ではおそらくあの人になるんじゃないかなというような考えはあるんですけれども、今年警察の暴力だとか人種差別など、様々な暴力の問題が湧き出ているアメリカで、新たなリーダーが誰になっていくのか、アメリカ人が今後どんなふうにこの社会を立て直していくのかというところを注目していきたいなと思っています。今月の初めに出した東洋経済の記事などもオンラインで見れますので、是非ご覧になっていただければ幸いです。
速水:ドキュメンタリー映画作家 ジャーナリスト 大矢英代さんに伺いました。ありがとうございました。