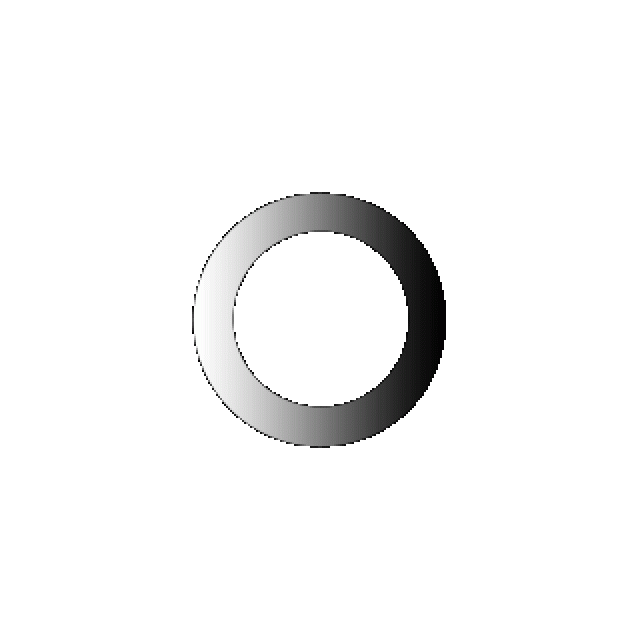エフエム山陰・BSSラジオ共同制作 防災特別番組「命と暮らしを守るパートナー~いざというときのラジオ~ 災害対策 編」
ラジオはいつでも、どこでも、あなたの暮らしに寄り添います。
エフエム山陰 と BSSラジオ、山陰に位置する2社のラジオ局が共同制作する特別番組。
- 9月18日(日)8時30分~8時55分
- パーソナリティー 大坂愛(エフエム山陰アナウンサー)、桑本みつよし(山陰放送アナウンサー)
山陰エリアをカバーする FM山陰と BSS山陰放送は、災害からリスナーの皆さんの生命や暮らしを守る目的で「災害時における情報発信 および 防災啓発に関する協定」を、山陰両県の全ての市町村と締結しています。
そして、2局共同で制作する防災番組も、今回で11回目。今回のテーマは「備える」。
日常は目立たなくとも、いざという時に備える人々の想いをリポートし、加えて備えることの必要性を伝えます。

"停電"に備える舞台裏…中国電力ネットワーク橋川課長にうかがいました
台風、大雪などで起こりうる停電。 2019年には鳥取で塩害による停電も発生しました。
停電を早期に復旧させるため、夜間・休日問わず24時間体制で社員が待機し、復旧班や広報班など合わせて数百人から数千人規模の防災体制を確保。早期復旧に努めていらっしゃいます。
加えて、関西、九州の電力会社といった広域範囲での協力体制や、隠岐などの離島においても海上保安庁などと連携し対応していらっしゃいます。
スマホ用の停電をお知らせするアプリも運用されていらっしゃいますので、ぜひ一度チェックしてみてください。
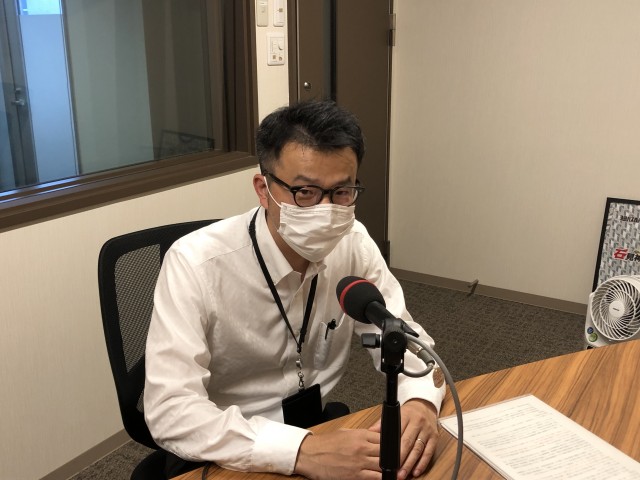
[写真]ご出演頂いた 中国電力ネットワーク橋川課長
鳥取県危機管理局 木山さんにうかがいました
台風等で警報や被害が出たとき、すばやく調査や対応を行っていらっしゃいます。
災害最前線で動いている各市町村との連携も欠かさないようにして状況把握に努め、
県のヘリコプターで上空から情報を集め、県民への周知をおこなっています。
加えて、災害に強いツールとして"ラジオ"を通じての県民への情報発信にも努めているとのことです。
水の備蓄について…山陰クボタ水道用材株式会社 伊藤隆生常務 にうかがいました
災害時に真っ先に必要なのが飲み水。備蓄の目安として、ひとり12リットルあれば2,3日分にはなるとのこと。
最近はローリングストックという、常日頃から備蓄と消費を繰り返していく動きも推奨されています。
例としてはウォーターサーバーの水を常に2パック確保しつつ、1本使用したら、新しいものを注文する、といった流れです。
特に避難所となりやすい公民館などに設置されていれば、飲み水の確保につながります。

[写真右]稲田アナ(左)と、山陰クボタ水道用材株式会社 伊藤隆生常務(右)
米子青年会議所に防災対策についてうかがいました
地域密着型の連携で災害対策を行っていらっしゃる米子青年会議所。
防災フェスタなどイベントも開催し、防災ついての啓発活動も積極的に行っていらっしゃいます。
改めて、災害対策への意識を強めるとともに、自分で守れる部分はしっかりと守っていきましょう。
あわせて、正しい情報を得るためにも「いざという時のラジオ」をお忘れなく…。
関連タグ